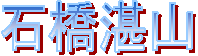Copy Right and Credit 佐藤清文著 石橋湛山
初出:独立系メディア E-wave Tokyo、2007年10月16日 本連載の著作者人格権及び著作権(財産権)は すべて執筆者である佐藤清文氏にあります。 リンク以外の無断転載、無断転用などをすべて禁止します。 |
|
第五章 文芸批評家石橋湛山 第一節 一廉の評論家 ヴィクトリア朝で三度首相を務めたベンジャミン・ディズレーリは小説家出身だったことで知られているが、日本でも、物書きから首相になった人物がいる。石橋湛山がその人である。戦後は政治家、戦前はジャーナリストとして活躍した湛山であるが、その出発は文芸批評である。湛山は早稲田大学卒業した後、二〇代を文芸批評家として活動している。しかも、たんなる一文芸批評家ではなく、将来を嘱望されている。一九〇七年(明治四〇年)、二五歳の生田長江は、『文学入門』の「批評と批評家」の章で、今の文学界には「批評家らしい批評家」がいないと嘆いている。しかし、湛山は、まぎれもなく「批評家らしい批評家」である。『東京毎日新聞』や『太陽』、『中央公論』、『日本及日本人』、『早稲田文学』などに文芸・思想・社会をめぐる批評を発表し、文学界からの湛山に対する文芸批評家としての評価は非常に高い。 『新小説』一九〇九年(明治四二年)八月号の「寸鉄」は二四歳の湛山を片上天弦や相馬御風、中村星湖以上の批評家と次のように賞賛している。 石橋湛山氏は青年評論家中にも若い方の側ださうだが、頭が余程利くと見える。説の是非は別として、議論をやる手腕が却々しつかり為してゐる。論を進めてゆく段取も整然として一糸乱れざるの風がある。天弦、御風、星湖等に比して確に論客たる資格に於いて、数段勝つていることは疑ひない。着実な方針で研鑽怠らずんば、他日見るべき一廉の評論家となられるであらう。湛山を含めたこの四人はいずれも早稲田大学に縁のある作家である。中村星湖(一八八四─一九七四)は、早稲田在学中の一九〇六年(明治三九年)に、「盲巡行」が泉鏡花に推されて『新小説』の懸賞一等、翌年には「少年行」が二葉亭四迷に選ばれて『早稲田文学』の懸賞長編小説に当選して刊行され、期待の自然主義作家である。湛山は一九〇七年(明治四〇年)七月に早稲田大学文学科を首席で卒業したが、その次席になったのが中村星湖こと中村将為である。また、片上天弦(一八八四─一九二八)は自然主義文学を擁護する作品を『早稲田文学』を中心に展開した文芸批評家であり、一九一〇年から母校で英文学とロシア文学の教授に就任している。湛山は、早稲田卒業後、後特別研究生として宗教研究科に一年間在籍していたが、その二年前に特別研究生に選ばれたのが片上天弦こと片上伸である。相馬御風(一八八三─一九五〇)は一九〇六年に早稲田を卒業し、口語自由詩運動を推進、『都の西北』の作詞者としても知られている。 湛山も、同じ年の三月に発表した『評論界瞥見』において、同時代の哲学・文学の批評に関して、具体的道筋を欠いた飛躍した議論、つめの甘い曖昧な概念定義や用法、体系性に乏しく整合性のない知識などで覆われ、何となくわかった気にさせているだけにすぎないと批判している。「寸鉄」の指摘する通り、湛山の具体性・厳密性への意志に貫かれた湛山の批評は天弦や御風、星湖とは比較にならない。実際、これら三人の文章は学術的な研究対象となりえても、今日読むに耐えない。それどころか、スター作家の島村抱月や生田長江を含め多くの作品も、文学史考察のための史料でしかない。ところが、湛山の批評は当時の言論の雰囲気を伝えるだけでなく、時代を超えて思想を訴えかけてくる。今日、湛山の文芸批評が顧みられることは少ない。湛山に対する関心は依然として高く、湛山論も絶えず発表されているが、文芸批評については軽く言及されるだけである。けれども、彼の批評は後に首相になった人物がこんなことを書いていたというレベルではない。それは近代文学への鋭い洞察に満ち、重要な示唆を与えてくれる。もし批評家を続けていたら、少なくとも、日本の批評史は変わっていただろう。「文壇の士以て如何となすか」(湛山『自己観照の足らざる文芸』)。 湛山が文筆生活に入ったのは明治四〇年代であるが、この頃、作家のペンネームをめぐって大きな変化が現われている。それまで、作家は、夏目漱石や森鴎外、石川啄木のように、号を用いていたが、武者小路実篤や有島武郎、志賀直哉など白樺派と呼ばれる作家たちは本名をそのまま使って作品を発表し始める。以降、号を筆名とすることは滅多に見られなくなっていく。片上天弦や相馬御風、中村星湖は号であるが、湛山は本名である。白樺派は大正期を代表する文学グループであると同時に、二〇世紀の日本文学の出発点である。湛山は、筆名の点でも、白樺派登場以降の時代に属している。 しかし、そんな先見性は時代に対して超然的な態度をとっていたからではない。湛山も、他の同時代人たちと同じ空気を吸っている。彼が生まれ、成長した時期、日本は近代国家としての方向を右往左往して模索し、諸制度を形成している。そういった社会的・歴史的背景の中で多くの人々が共有している問題を徹底的にある認識に基づいて突きつめ、さらに踏み越えて独自の思想を形成しているところに、湛山の時代を超える独創性がある。 第二節 人間万事塞翁が馬 石橋湛山は、鹿鳴館時代の一八八四年(明治一七年)九月二五日、東京市麻布区芝二本榎(現東京都港区二本榎)において、父杉田湛誓と母石橋きんの長男として出生している。幼名は「省三」といい、一九〇二年(明治三五年)三月八日に「湛山」と改名している。 父の湛誓(一八五五─一九三〇)は日蓮宗の僧侶であり、当時、東京大教院(現立正大学)に助教補(助手)として勤務している。後に「日布」と改名し、大正一三年、総本山身延山久遠寺第八一世法主に選ばれている。明治維新後から始まった廃仏毀釈によって日蓮宗も大打撃を受け、湛誓を含めた若き僧侶は再建のため、各地で学校を設立したり、雑誌を発行したり、啓蒙活動に日夜励んでいる。母のきん(一八六八─一九三三)は江戸城内の畳表一式を請け負う大きな畳問屋石橋藤左衛門の次女である。石橋家は日蓮宗承教寺の有力な檀家で、同寺院内に所在した東京大教院に在学中の湛誓と親しい間柄である。「私は事情があって、この母方の姓を名乗って、石橋というのである」(『湛山回想』)。 湛山の前半生はすんなりと進んではいない。思い通りにならないことが多いが、それが湛山を湛山たらしめている。一八八五年(明治一八年)、父湛誓が郷里山梨県南巨摩郡増穂村(現同郡増穂町)の昌福寺住職へ転じたため、母きんと共に甲府市稲門(現伊勢町)へと転居する。一八八九年(明治二二年)四月、稲門尋常小学校に入学、三年生の時、父と同居することになり、稲門から約二〇km奥まった増穂村の小学校に転校する。学校から帰ると、父から漢文の素読の指導を受けている。 素読破意味がわからなくても、暗証できるまでに繰り返し読むという伝統的な学習方法である、しかし、それは、漢文の真の魅力である押韻や平仄を味わえない対訳文である。江戸時代に来訪した朝鮮通信使は、新井白石などの例外を除き、役人や知識人たちがあまりにも漢文ができないことに呆れている。李氏朝鮮では、漢文を原文で使いこなせなければ、文官になることなどできない。「私のごときは、子供のころ、家庭の事情で、幾分はまだ漢学教育の名ほりの中に育ったものだが、それでいて、今実際には、論語といえども、ろくに読めない。少しばかりの漢字を習ったとて、漢籍や仏典を理解するのに、なんの足しになるものでもない」(石橋湛山『「当用漢字」と「現代かなづかい」の問題』)。 小学校時代、都会のお嬢さまだった母は湛山を「東京風のお坊っちゃん」として育てようとしている。木登りや水泳を禁止し、「財布を持って歩いたことがない」という通り、お小遣いを与えず、欲しいものがあればそれを現物支給している。もっとも、水泳に関しては、当時、川泳ぎによって赤痢に感染する危険性があったという事情もある。そのせいか、身体が小さく、運動神経もよくはなく、体育の成績はいつも落第すれすれである。入隊した際も、器械体操などで苦労している。結局、生涯に亘って湛山は木登りはできず、金槌のままである。また、この頃は明治政府が発行した貨幣だけでなく、江戸時代のものも流通しており、教室でその違いを教師が教えていたが、お金に接した経験がない湛山にはまるでちんぷんかんで恥かしい思いをしている。湛山は、そこで、家から小銭をかすめるようになってしまう。「あんまり束縛する教育は良いものではない」(『湛山回想』)。 日清戦争が勃発した一八九四年(明治二七年)、父湛誓が静岡市池田の本覚寺住職に転じることになった際、湛山は山梨県中巨摩郡鏡中条村(現南アルプス市鏡中条)の長遠寺住職望月日顕(一八六五─一九四三)に預けられる。湛誓は、自分の子を育てるのは難しいので、他人のこと交換する方がよいという孟子の教え「古者易子而教之」に倣ってこの教育方針を決めている。日謙も後に身延山久遠寺八三世法主になったほどの僧侶であるが、厳格であった父に比して、懐の広い寛容な性格の人物で、湛山自身は「もし望月師に預けられず、父の下に育てられたら、あるいはその余りに厳格なるに耐えず、しくじっていたかもしれぬ。(略)望月上人の薫陶を受けえたことは、一生の幸福であった。そうしてくれた父にも深く感謝しなければならない」(『湛山回想』)と言っている。一九五七年から八二年まで日本医師会会長を務めた「武見天皇」こと武見太郎も、増田弘の『石橋湛山』によると、日謙に影響を受けた一人である。これを機に、湛山は父母との親子関係は事実上断たれ、手紙を出しても、返事が返ってくることはない。 一八九五年(明治二八年)四月、高等小学校二年で山梨県立尋常中学校(現山梨県立甲府第一高等学校)に合格する。しかし、二度落第している。最初は勉強についていけなかったからであり、次は慢心が理由だったと湛山は説明している。この間、湛山は学校への月謝を買い食いで使いこみ、日謙は黙って学校に不足分を支払っている。賢いが、ムラのあるやんちゃな生徒だったというわけだ。この落第のかげで、湛山は、一九〇一年(明治三四年)四月、大島正健校長と出会うことになる。大島正健(一八五九─一九三八)は札幌農学校(現北海道大学)第一期生としてウィリアム・S・クラーク博士の薫陶を受けたキリスト教徒で、アメリカの民主主義・個人主義を教育方針として打ち出す。湛山は彼から大変に影響され、晩年まで枕元に日蓮遺文集と並んで聖書を置くほどである。 当時の湛山を知る上で興味深いのが「紺タビ」のエピソードである。『タビ談義』(一九五一)によると、日清戦争直後の頃、地方ではタビは白木綿の自家製が一般的で、金属製のコハゼもまだなく、ラブの首についた共切れの木綿の紐で足に縛りつけている。けれども、紺タビになると、その共切れを入手するのが難しく、店で仕立てなければならない。しかも、このオーダーメードは洗濯すると、色落ちがするし、また穴が開いても、きれいに修繕できない。紺タビは洒落者の履く、贅沢品であり、湛山は中学入学から結婚するまでこれを愛用している。媒酌人の三浦銕太郎夫人から、紺タビは不経済だから、白タビにするように戒められ、それに従っている。戦後、吉田茂首相が白タビを履いているのが「貴族趣味」だと批判された際、湛山はそれを鼻で笑っている。紺タビの流行はすたれたが、湛山によると、流行は黒の朱子タビで、依然として白タビはエコノミー・クラスの実用品でしかない。 日英同盟締結の年一九〇二年(明治三五年)三月、山梨県立第一中学校を卒業する。同期生五三名中席次は一七番目である。同年四月、医師志望の湛山は第一高等学校(現東京大学教養学部)受験のため上京、正則英語学校に通い、七月に受験したものの失敗、再度臨んだ翌年の試験にも不合格となり、早稲田大学高等予科の編入試験に合格、九月に入学する。日露戦争勃発の年である一九〇四年(明治三七年)九月、湛山は予科を修了し、大学部文学科(現文学部)哲学科へ進級する。校長(現総長)は鳩山和夫であり、後に衆議院議長になった人物で、その息子が鳩山一郎である。鳩山一郎は初代自由民主党総裁として首相に就任し、その後継総裁に選出され、首班指名を受けたのが湛山である。当時の早稲田文学科の講師陣は、高田早苗、煙山専太郎、安部磯雄、内ヶ崎作三郎、坪内逍遥、金子馬治、島村抱月、姉崎正治、波田野精一、岩谷小波、田中王堂など非常に豪華であったが、湛山は、中でも、王堂(一八六八─一九三二)から多くの哲学的示唆を受け、その弟子であると公言してはばからない。王堂はシカゴ大学でジョン・デューイに師事し、プラグマティズムを初めて日本に輸入して哲学者である。明治末から大正にかけて自然主義文学が流行した際、彼は個人主義・自由主義に立脚して、それを厳しく批判している。 ここまで見てきて気づかされるのは、湛山がアメリカ的思考・認識に馴染んでいた点である。いわゆる開国のきっかけは黒船来航であるにもかかわらず、近代国家形成の際、ヨーロッパを参考に諸制度を採用している。産業革命を達成し、世界最大の工業国に成長したアメリカは間違いなく二〇世紀に大国となると見られている。しかし、日本の帝国主義化とアメリカのそれとが平行していたこともあって、学ぶべきお手本ではなく日本はアメリカを対立する相手と捉えている。明治末くらいから日米の未来戦記の本が刊行され、第一次世界大戦後は一つのジャンルと呼べるまで流行している。アナーキズムを含む社会主義思想がアメリカを経由して伝来し、またキリスト教徒は渡米することが多かったけれども、日本の文学・哲学のメインストリームは、事実上、太平洋の向こう側を無視し、このヨーロッパ大陸偏重は第二次世界大戦後もしばらく続いている。一九一九年(大正八年)、デューイ自身が東京帝国大学で二ヶ月に及ぶ講義「哲学の改造」を行うが、学生たちの反応に失望している。王堂もキリスト教徒であり、湛山のような留学経験もない非キリスト教徒、より正確には日蓮宗の信徒がアメリカ哲学の影響を受けるというのは、当時としては珍しいケースである。それどころか、アメリカ的志向を消化し、後の自然主義文学批判が示すように、王堂以上に自分のものにしている。 アルバイトに励んでいる学生も多い中、あまり器用な方ではないこともあって、湛山はほぼ学業に専念している。優秀な成績で早稲田を修了し、湛山は文筆生活に入る。もっとも、湛山は文芸批評家になりたくてなったわけではない。明治四〇年代当時、私学出身者には、新聞界か文芸界くらいしか道が開かれていなかったからである。官界・教育界・実業界などは帝大や東京高等師範学校(現筑波大学)、東京高等商業学校(現一橋大学)といった学閥が物を言うのが現状で、うまく入れたところで、私学出は給与の面でみじめなほど待遇の差がある。ただ、私学の中でも慶應義塾大学だけは歴史も古く、福沢諭吉の功績もあって、実業界に人材を輩出している。どんなに優秀であっても、湛山のような早稲田大学の出身者は東京で職を求めようとするなら、新聞界か文芸界に進むほかない。 早稲田の関係者も現状を承知しており、卒業生への職の斡旋を積極的に行っている。早大の創設者大隈重信を総裁として大学関係者が組織した大日本文明協会が海外の名著を翻訳して紹介する企画をしていたが、これには卒業生へ仕事を提供する目的があり、一九〇八年(明治四一年)七月、湛山もここから『世界之宗教』という本の編纂を委託されている。ところが、東京毎日新聞社への就職が決まり、この仕事に携わる時間的余裕がなくなってしまう。また、一九〇九年(明治四二年)一二月一日より一年間の軍隊生活に入ったため、序論の「宗教之本質」だけ執筆している。残りは大屋徳城、大杉潤作、小沢一が担当し、一九一〇年(明治四三年)三月一〇日に『世界之宗教』は刊行される。いずれも早稲田大学哲学科の出身者で、大屋徳城は湛山の一年先輩、大杉潤作と小沢一は同期である。 湛山は、『湛山回想』の中で、「私を文筆界に導いた恩人」として島村抱月の名を挙げている。抱月は早大の講師であったが、湛山は王堂に師事していたこともあって、在学中は面識はあまりない。けれども、抱月は面倒見がよく、卒業生が困っていると、よく手を差し伸べている。レフ・トルストイの『復活』を上演する際にも、無名の中山晋平に挿入歌の制作を依頼し、それに応えて完成したのが「カチューシャの唄」である。湛山も、卒業後、抱月に何かと目をかけてもらっている。 島村抱月(一八七一─一九一八)は、一八九四年(明治二七年)、東京専門学校(現早稲田大学)卒業後、『早稲田文学』の記者を経て、一八九八年(明治三一年)、読売新聞社会部主任に就任する。その後、早稲田大学文学部講師となり、一九〇二 年(明治三五年)から〇五年まで早稲田の海外留学生として英独留学する。四年後に帰国すると、早大文学部教授に就任し、『早稲田文学』を主宰して自然主義文学運動の後押しをしている。当時の抱月は、八〇年代の浅田彰のように、ヨーロッパの最新の文学・哲学を手に颯爽と現われ、既存の批評家たちを古びたものにしている。この旬の批評家による「囚はれたる文芸」や「文芸上の自然主義」、「自然主義の価値」などを所収した『近代文芸之研究』(一九〇九)は言論界で熱く議論されている。 また、抱月は文学理論だけでなく、演劇の方面でも活躍している。彼は、一九〇六年(明治三九年)、坪内逍遥と共に、会頭に大隈重信を迎え、文芸協会を創立している。当初は役者の技量が伴わないこともあって苦戦するが、養成所を設立して人材が育ち始めると、評判を博するようになる。しかし、一九一三年(大正二年)、抱月と看板女優の松井須磨子とのいわゆる不倫スキャンダルが起こり、二人は文芸協会を脱退する。同年七月、抱月は須磨子と芸術座を結成するが、実は、湛山もそれに参画している。実際、湛山は、抱月との関係から演劇にも詳しく、『劇壇の変化』(一九一二)において明治期の演劇史をダイナミックに要約し、芸術座登場以前の劇壇を「発酵の時代」と呼んでいる。当時はテレビもラジオもなく、映画はまだ海のものとも山のものともわからない代物で、演劇こそ民衆にとって最大の芸術的娯楽である。歌舞伎と違って、女優も登場する新劇は近代社会における芸術性と商業性の止揚が図られ、非常な活気を呈している。 翌年、レフ・トルストイの小説『復活』を抱月が翻訳・脚色し、須磨子がカチューシャを主演した舞台が評判となり、各地で上演され、爆発的な人気を獲得する。さらに、一九一五年(大正四年)、彼女が歌う劇中歌「カチューシャの唄」(作詞島村抱月=相馬御風・作曲中山晋平)が『復活唱歌』のタイトルでオリエント・レコードからレコード化され、事実上、近代日本初の流行歌となっている。また、これに便乗した業者が馬蹄形の髪留めを「カチューシャ」として売り出し、この名称は現在でも使われているだけでなく、それが似合う三つ編みのヘアー・スタイルも「カチューシャ」とも呼ばれている。この時の須磨子は、その人気と実力の点で、八〇年代のマドンナといったところで、今日の日本の女優や歌手と比較にならない。湛山がいたのはこうしたセレブな雰囲気である。 一般的に論じられる湛山はモードの関係で考察はほとんど見かけない。しかし、湛山は紺タビのエピソードが示しているように、流行には割りに敏感で、なおかつ時代の最先端にいることも少なくない。中学時代、身体を鍛えるために剣道を始めたが、早大入学後、テニスを知って、それにはまっている。「汗くさい面をかぶって、薄暗い屋内でする剣道がいやになり、それっきり、ついにはやめてしまった。遊戯はやはり戸外でするものの方が床である」(『湛山回想』)。また、一九三五年(昭和一〇年)、湛山は早大商学部に在籍していた次男の石橋和彦にスキーに誘われ、これにも魅了されている。湛山は若大将シリーズの先を行っていたわけだ。さらに、電化製品の購入も早い。もし今生きていれば、おそらくバラク・オバマばりにIT技術を駆使しているに違いない。 もっと驚嘆させられるエピソードがある。一九二二年(大正一一年)、鎌倉に自宅を持った際、湛山はトイレを水洗の腰掛式にしている。しかし、その頃、鎌倉は水洗トイレに対応する下水道が完備していなかったため、『便所と洗面所』(一九五二)によると、湛山は浄化設備をつけ、しかもそれをメタン・ガスが発生する装置にし、台所燃料を補うようにしている。このシステムを三〇年間以上使い続け、一度の故障もなかったと言う。 抱月は、芸術と経営の「二元の道」を提唱するなどその後も旺盛な活動を続けたが、一九一八年(大正七年)一一月五日、スペイン風邪により急死する。湛山は、その一ヶ月後、『早稲田文学』に「四恩人の一人」と題して「私は生まれて以来、島村先生の死に会ったほど力を落としたことはない」と追悼文を寄せている。一九一九年(大正八年)一月五日、松井須磨子は彼の後を追って芸術座の道具部屋で縊死し、芸術座も解散する。「もし須磨子が現れるなら、私といえどもいつ島村氏にならぬとは限らぬ」(『湛山回想』)。 湛山は、一九〇八年(明治四一年)、抱月の紹介で小杉天外が企画した『無名通信』の記者に採用される。ところが、諸般の事情により発刊が延期されたため、抱月は湛山を『東京毎日新聞』に推薦する。『東京毎日新聞』は日本初の新聞とされる『横浜毎日新聞』を前身とし、一九〇六年(明治三九年)七月に、『毎日新聞』から改称している。その際、衆議院議員で社長の島田三郎は大隈重信に経営を譲り、三年後、大隈の報知新聞社に買収される。大隈は、一般向けの『報知新聞』に比して、『東京毎日新聞』をオピニオン紙にする方針を立てる。そのため、大隈は早稲田で教授を務めていた田中穂積(一八七六─一九四四)を副社長兼朱筆に抜擢している。彼は、一九三一年(昭和六年)、第四代早稲田大学総長に選任される。湛山は入社当初は三面(社会面)に配属されたが、後に二面(政治文芸面)に異動となり、文芸批評を執筆している。記者生活を始めた頃、『湛山回想』によると、万年筆はまだなかったので、ペンとインクで机の上に置いた原稿用紙に記事を記すものだと思っていたら、ベテランは硯で墨を擦り、手に巻紙を持って毛筆で認めていたことに驚いたと述懐している。加えて、一九〇九年(明治四二年)四月、抱月から主催する『早稲田文学』の「教学評論」欄を隔月で任せられている。 ところが、その年の八月、新聞社の内紛に巻き込まれ、湛山は朱筆の田中穂積と共に退職せざるを得なくなる。事の発端は、その春頃から、大隈率いる進歩党(後の政友会)の内部で犬養毅と他の幹部との間で対立が生じ、それが社内にも反映されて、記事が両派の綱引きになってしまう。犬養は「犬は養えるが、人は養えない」と揶揄された人物で、政策通であっても、人心掌握に難があり、その後の政治家生活でも何度もそれが露呈する。新聞は経営不振に陥り、朱筆が退職し、湛山も行動を共にする。その後、湛山は『無名通信』や『読売新聞』、『文章世界』、『早稲田文学』などに批評を寄稿して食いつないでいる。 同年一二月、湛山は、関与三郎と大杉潤作の付き添いで、麻布の砲兵第三連隊に入営する。学生の間は徴兵が延期されていたが、フリーとなったためそうもいかない。そこで、湛山は当時あった一年志願制度を利用する。これは、中学以上の卒業生で、一年間の経費一〇八円を納付すると、特別教育を受けられて、伍長ないし軍曹で除隊できるという制度である。通常の徴兵兵より入営期間が短く、待遇もよいので、多くの若者が利用している。軍曹に昇進した者は、翌年見習い士官として三ヶ月の演習召集を受け、終末試験で合格すると、予備少尉に任ぜられる。とは言うものの、軍隊生活は厳しいと噂で聞かされていたので、びくびくしていたのだが、配属された第二中隊第三班で湛山は厚遇を受ける。班長の伍長から丁寧に挨拶され、新兵係の鈴木少尉に中隊将校室に呼ばれて餅菓子をご馳走になっている。早稲田出の元新聞記者という経歴から社会主義者と勘違いされたからである。社会主義はその頃の体制にとって脅威として感じられ、入隊した際にも、社会主義者たちは軍隊にとって頭の痛くなるトラブルをしばしば巻き起こしている。共産主義はまだ一般的な用語ではなく、急進派はほとんど社会主義者に括られている。入営中の一九一〇年(明治四三年)五月、明治天皇暗殺計画の疑いで社会主義者が大量に検挙・逮捕され、翌年の一月、幸徳秋水他一一名が処刑されるという大逆事件が起きている。湛山が社会主義者と疑われていたのはこの時期で、軍は好遇をしながら、彼を四六時中監視していたのが実態である。もっとも、この疑念は半年もしないうちに解け、一般の新兵と同じ待遇になる。一九一一年(明治四四年)一一月、湛山は軍曹で除隊、翌年九月に見習い士官として三ヶ月召集を受け、終末試験を合格、少尉の任官辞令を交付される。 入営直後六〇kgあった湛山の体重は四八㎏に落ち、それは除隊するまで回復しない。おまけに、食事も口に合わず、高所恐怖症にも苦しめられている。しかし、この一年三ヶ月の生活を通して、湛山は軍隊を見直している。軍隊は時代離れした精神主義が蔓延してなどおらず、合理性に基づいた組織であり、そこでの思考・行動には論理的な意味・機能がある。中でも、衛生・健康に関する基準は一般社会よりもはるかに高い。軍隊は、『湛山回想』によると、「一種の社会の縮図」であり、「一種の教育機関」である。しかし、逆に言えば、軍隊の意義はその徹底した合理主義にあって、もしそれが失われれば、極めて危険な組織と化す。戦時中も含めて後に、湛山は軍部を合理主義から軍部を批判することになる。軍隊を賞讃しながらも、その組織の目的には、入営以前にも増して嫌悪感が増している。軍隊経験は彼に反戦への意思を強固なものにする。 湛山は、除隊直後、田中穂積から東洋経済新報社の記者の職を紹介される。同社は経済を専門としていたが、明治四〇年代、自然主義文学の流行や個人主義・自由主義の勃興という時代風潮に応えるため、社会批評を中心とする月刊誌『東洋持論』を刊行したものの、編集記者が足りない状況である。主催者の三浦銕太郎(一八七四─一九七二)は田中穂積と早稲田の同窓生である。湛山はその面接を一二月に受けて採用になる。翌年一月から記者として活動し始め、文芸批評を『東洋持論』に次々と発表する。しかし、一九一二年(明治四五年)一〇月、『東洋持論』が休刊となり、湛山は『東洋経済新報』の記者へと異動する。この人事により、湛山は文芸批評に代わって、政治・経済・社会を対象とする記事を書くことが中心となる。 湛山が異動してから『新報』の文体に大きな変化が起きている。文芸の世界では、すでに言文一致体が使われていたけれども、それ以外の領域では依然として「漢文くずしの文章体」が一般的である。文芸誌の『東洋持論』の文体は口語であったが、『新報』は文語である。と言うよりも、当時の新聞は、読者が離れるのではないかと危惧して、「漢文くずしの文章体」を使い続けている。しかし『新報』一九一三年(大正二年)七月五日号は巻頭に口語体への変更に関するに一ページ大の社告を掲載する。この筆者は湛山である。ただし、「金融市場」と「社説」は据え置かれ、紙面全体が改まったのは一九一五年(大正四年)一月からである。『新報』は政治・経済の雑誌媒体では口語体の変更したのは早い方で、急進的でさえある。日本近代文学における最初の海内は言文一致である。湛山が文芸から政治・経済の書き手に転身すると共に、それがその外にも広がっていったのは象徴的であると言わざるを得ない。 第三節 自然主義文学批判 湛山が文芸批評家として活動していた時期は、自然主義文学が流行していた頃である。この潮流をめぐって肯定派と否定派の間で激しい論争が繰り広げられている。 人間を客観的かつ経験的に描かなければならないとする自然主義文学はゴンクール兄弟やエミール・ゾラといった一九世紀のフランス文学から生まれ、その後、欧米に広がっている。日本では、日清戦争と日露戦争の間にゾラを中心として西洋の作品が紹介され、影響されて小杉天外が『初すがた』(一九〇〇)、永井荷風が『地獄の花』(一九〇二)を発表している。しかし、本格的に書かれるようになったのは日露戦争後の一九一〇年代であり、社会現象と呼べるくらいに流行している。 一九〇六年(明治三九年)、島崎藤村が被差別部落出身者を主人公とした『破戒』を公表すると、多くの賞讃の声がそれに寄せられ、翌年、田山花袋が『蒲団』において性をめぐる中年作家の葛藤や欲望を描き、評判を呼ぶ。『早稲田文学』や『読売新聞』といった早稲系の活字メディアがこれをプッシュし、自然主義は文壇のヘゲモニーを獲得する。徳田秋声や正宗白鳥、近松秋江、真山青果などの作家がこの動きに同調するように登場している。日本の自然主義は人間と社会を自然科学的に観察すのではなく、因習や権威からの解放を求めて自己を告白するという図式に陥ってしまい、次第に身辺雑事を描写するリアリティショー的傾向が強くなり、私小説に至ってしまう。 この自然主義文学を擁護したのが島村抱月を代表とする早稲田系の文学者たちである。湛山は、抱月に極めて近く、『早稲田文学』にも寄稿している。しかし、湛山の批評は抱月と意見を異にし、明らかに自然主義文学に批判的である。けれども、その一方で、湛山の思想的師匠である田中王堂の主張とも違っている。話にならないと一刀両断がしない。湛山は一方的な擁護も批難もしない。その意義を認めた上で、問題点を指摘する。 湛山が今でも読み得る理由として確かな歴史認識がある。彼は、『明治時代の文学に現れた思想の潮流』(一九一二)において、明治の文学史を要約し、自然主義文学について論じている。 明治に入ると、まず西洋事情を滑稽に描いた仮名垣魯文を代表とする戯作が始まり、一八七七年(明治一〇年)に西南戦争が勃発し、その結果、明治維新右派が壊滅すると、政府は威信左派である自由民権派の弾圧に回り、それに対抗するプロパガンダの政治小説が盛んに書かれる。東海散士のように、形式は戯作を脱しているものの、文体は依然として漢文書き下しくずしで、「西洋自由思想の憧憬渇仰時代」の文学である。しかし、明治一四年の決定により一〇年後の国会開設が決まると、自由民権の叫び失せ、また鹿鳴館のような極端な欧化主義への反発も生じ、政教社が国粋保存主義を提唱するや、仏教や国学が息を吹き返す。『源氏物語』が復刻され、志賀矧川(重昂)の『日本風景論』が愛読されていてた保守的な時期であるが、西洋化に向かって一心不乱に突進するだけから自分自身を省みることに気がついた最初の時代である。 従前の文学は西洋事情の紹介や政治思想の宣伝などの道具となってしまい、「清志」から離れた「死物」でしかない。その「清志」を発展させるために自由詩や言文一致の運動が盛んになる。新大使運動も重要であるが、それ以上に画期的だったのが坪内逍遥の『小説真髄』(一八八五)である。逍遥は近代小説の「神髄」を近代リアリズムの手法と心理描写であると明確に意義づける。加えて、『当世書生気質』でそのリテラシーを実践して見せる。近代日本文学はこの二冊によってようやく進むべき方向を発見する。 逍遥の示唆を受けて、日清戦争の頃まで、写実小説・人情小説が流行し、その中心が尾崎紅葉グループである。しかし、彼らは近代リアリズムや心理描写が何たるかをまったく理解しておらず、浅はかな作品ばかり著わしている。着物の縞柄や髪の結い方を精写することがリアリズムだと思っている有様だったが、戯作や漢文書き下し調しか知らない読者にとっては新鮮に感じられ、愛読されている。だが、日清戦争がこの状況を一変させる。初の近代戦争は近代リアリズムや心理描写の何たるカを強烈に文学者たちに覚醒させる。「勃興の英気と哀愁の感情とを事実として味わった」読者は幸田露伴を歓迎し、斎藤緑雨や樋口一葉も次いで登場する。とは言っても、この時期に至ってもまだ真に近代小説の「神髄」を理解してもいない。「人情とは何である。観念は何である。所詮は我れに外から与えられたものではないか。我が希求そのものではない。しかれば則ち今までの明治の文学は、漸次に主観に入り、我れの明瞭なる認識に近づいて来たとはいうものの、これを引き括めていえば、未だ我が周囲を眺め廻して、ここに満足を求めんとしていたにすぎなかった」。 そこで登場するのが自然主義文学であるが、湛山は、『明治時代の文学に現れた思想の潮流』において、その流行の理由を同時代人として次のように分析している。 しかるに日露戦役じゃあらゆる方面において我が国民の自覚を促したるが如く、文学においてもいわゆる自然主義の勃興となって、ここに全くあらゆる教健と制度と感情と思想との制縛から離れて、端的にわれを見んとするの努力が起った。これけだし文学のみが独りかく進んだのではない。明治文明の全体が、その政治上におけると経済におけると、その他百般の社会制度の上におけるのとを問わず、既に一通りは西洋文明に倣って改廃すべきは改廃し、輸入すべきは輸入して、而してその結果は、日露戦役における成功となって現れたのであるが、さてなお考えてみるのに、何者か未だ足りぬものがある。落ち着かぬところがある。その足りぬものは何か。落ち着かぬのはどこか。この不満不足を早く感じて、而して明らかな我れの意識からの原因を尋ね出さんとしたものが、すなわち自然主義文学であった。自然主義文学は、これを理論づけんとする人々によって主張された説には大なる欠陥があったけれども、しかしその歴史的意義はかくの如く深きものであった。自然主義文学は、日本的近代化を達成して日露戦争で勝利し、脱亜入欧を果たしたという意識が生まれた結果、目指すべき目標を失い、人々は空虚感に襲われる。その欠落感を埋めるために、内向したのが自然主義文学である。しかし、これを擁護する理論には欠陥があり、その可能性を十分に発揮できなかったけれども、歴史的意義は認められる。 湛山はこうした自然主義文学に関する認識を他の作品でより詳細に考察している。自然主義文学の秘められた可能性と実現できなかった原因を彼は解き明かすが、それを見ると、いかに近代小説の「神髄」を理解していたかがわかる。 湛山が自然主義文学を評価する点は個人主義的傾向であり、それは「自己観照」、すなわち自己確立の問題である。彼は国家に対する個人の立場と封建的制度からの解放を擁護する。「今は絶対者倒潰の時代である。そしてまさに来るべき時代は智見の時代でなければならない。(略)すべての方面において人間というものが光を放って来た」(『絶対者倒潰の時代と智見の時代』)。文化というものは人間がその欲望を満足させるために、生み出したものである。「自我とは(略)時々に起り来るよく望である。この欲望の満足が人間哀心の願望、最始最終の目的である。(略)而してこの欲望統一の機関として人が工夫し出したものが即ち宗教、哲学、道徳、政治、法律その他一切の文化である。国家というものも、かくして出来たものである」(『没我主義とは何ぞや』)。同様に、国家も個人として生きるために組織されたのであって、「人が国家を形造り国民として団結するのは、人類として、個人として、人間として生きる為めである。決して国民として生きる為めでも何でもない」(『国家と宗教及文芸』)。そのため、湛山は、『イプセンの「人形の家」と近代思想の中心』(一九一二)の中で、個人主義を自分に閉じこもり、社会に対する無関心な態度ではないと言っている。「社会的要素を無視し得ない個人主義」であり、「現実を改造して我の要求に合致するものにしようとする個人主義」でなければならない。「人生自然を最美最完なる」ものとしてその改良を放棄すべきではない。 自然主義文学は露悪趣味や出歯亀文学と批判されているが、湛山はその見方を斥ける。しかし、彼は、『問題の社会化』(一九一二)において、社会が変わっていくにもかかわらず、いつまで経っても、自然主義文学は「束縛」からの「自由」や「解放」をスローガンを掲げていると批判する。そういった「消極的」な態度ですむ時代は過ぎ去り、「個人の解放」や「伝習の破壊」の時代を超えて、「積極的」に世界を改良していくシナリオを提示する必要がある。結局、自然主義文学は創造的破壊ではない、ただの破壊に終始している。しかし、文芸には大いなる力がある。「文芸は実に政治、道徳の批判者である。又政治、道徳の改革者である。彼は、吾人の欲望と道徳、法律、習慣等との間に矛盾撞着の起った場合に、最も合理的なる方法を用いて、この矛盾を解き、人生を滑らかにすべき使命を負えるものである」(『自己観照の足らざる文芸』)。 社会改良という公共性・公益性への寄与どころか、文学者たちはとんだ俗物ぶりを見せる。一九〇七年(明治四〇年)六月、内閣総理大臣西園寺公望は、読売新聞社の竹腰三叉に相談した上で、自宅に文学者二〇人を招待する。内閣総理大臣が文学者を招いたのはこれが初めての出来事であり、後に「雨声会」と呼ばれるこの会合は、以降、主客を交代して数回開かれている。六月一七日から三日巻続いたこの会の出席者は徳田秋声、巌谷小波、内田魯庵、幸田露伴、横井時雄、泉鏡花、国木田独歩、森鴎外、小杉天外、小栗風葉、広津柳浪、後藤宙外、塚原渋柿園、柳川春葉、大町桂月、田山花袋、島崎藤村である。人選に携わった近松秋江は、「卑しい文士風情が雨声会一夕の宴席に招待されることを無上の栄誉と感佩するのも無理はなかろう」と述懐している。父親から「小説なんか書いている道楽者はくたばってしめえ」と言われたのに対するユーモアとして、長谷川辰之助が筆名を「二葉亭四迷」にした通り、当時の文学者の社会的地位は確かに低い。けれども、夏目漱石、二葉亭四迷、坪内逍遥は出席を断っている。二葉亭は内田魯庵に、そんな場所に行ってられるかと相手にもせず、逍遥は丁重な手紙を送って辞退したが、漱石は「ほととぎす厠なかばに出かねたり」と一句添えて返答している。自然主義文学は名もなき人を主人公にして描く以上、市井の人々と同じ高さの視線を持っていなければならないのに、上からどう見られているかが気になって仕方がなかったというわけだ。屈折した権力意に満ち満ちた識彼らにとっては個人の解放や因習打破など口実にすぎない。 湛山は『評論界瞥見』において「小説というものは文明批評の一形式だ」と言っているが、これほど近代小説の「神髄」を把握したフレーズもない。近代小説は近代社会に出現した普通の人々をとり扱う市民の文学である。とり扱い方は社会的・客観的である。登場人物は等身大で、その性格・心理・志向は社会が表われたものである。社会的仮面、すなわちペルソナを被った本当の人間あるいは人間の真の姿を描写しようとすることから、しばしば因習的とならざるをえなくなる。しかし、反面、登場人物の心理に自由にかつ深く立ち入ることができ、それによって読者は平凡でどこにでもいそうな主人公に共感することも少なくない。近代小説の真の主役は近代社会である。そこから社会改良への動きが生まれてくるのは必然的である。 ところが、自然主義文学は。近代小説における社会性を見出せない。社会を扱うために、作品が書かれるのであって、そのとり上げ方は客観的でなければならぬ。けれども、自然主義文学者は客観性ではなく、主観性に傾倒する。抱月は、『文芸上の自然主義』(一九〇八)において、自然主義を主観主義的なロマン主義の一種とさえ見ている。関心が外向的でなければならないのに、「未だ我が周囲を眺め廻して、ここに満足を求めんとしていた」という日清戦争後と同じことが繰り返されている。自然主義文学は近代小説の持っていた可能性を具体化することなく、社会性を欠いたリアリティショーの私小説に堕していく。 第四節 アメリカの自然主義文学 従来、湛山の自然主義批判は田中王堂の影響として論じられている。しかし、王堂が自然主義文学を認めなかったのに対し、湛山はこの文学には本来社会改革を行えるだけの力があるのを見抜いている。湛山は、むしろ、王堂以上に同時代のアメリカと共鳴している。実は、アメリカの自然主義文学はまさに湛山の主張を体現している。彼らは社会改良することこそ文学の役割だと信じて行動する、雨声会に呼ばれた云々で一喜一憂している日本の作家たちの姿を見ると、志の低さに唖然とさせられる。 一八九〇年頃、雑誌の発行人たちはシリアルや清涼飲料など全国展開を視野に入れる企業から広告収入を集めて、価格を下げ、ニュース・スタンドで不特定多数の読者に販売するという方式を思いつく。『マックリュアーズ・マガジン』や『レディーズ・ホーム・ジャーナル』、『サタデー・イブニング・ポスト』、『コスモポリタン』などがこの新タイプに含まれる。この三文雑誌の読者は学識の高い教養豊かなではエリート層ではない。一般庶民である。急増する都市の人口を背景に、新聞や雑誌の出版ブームが起きている。誰でも読めるように、語彙も少なく、平易な文体で記され、内容も具体的で身近な実感できる話題にする。その頃のアメリカでは、政府は企業活動に介入すべきではないという信念が強くあり、そのため、絶望的に貧富の格差は拡大し、全米中に不正が横行する。全米各地で社会改良を訴える進歩主義運動が勃興する。雑誌の発行人たちは、渦巻く不正に対する憤りから社会改良の機運が高まっているのなら、これを前面に出せば、売れると思いつく。 発行人の思惑とは別に、その雑誌で活動した作家やジャーナリストたちは世間で横行する不正や腐敗、強欲への義憤にかられ、ペンを通じて社会改良の必要性を真剣に訴えている。リンカーン・ステッフェンズは『都市の恥』(一九〇四)で政界の腐敗を糾弾し、アイダ・M・ターベルは『スタンダード石油会社の歴史』(一九〇四) で石油カルテルの不正を暴露、フランク・ノリスは『蛸』(一九〇四)で小麦農民による横暴な鉄道会社への抵抗を描き、エドウィン・マーカムは『囚われの子供たち』(一九一四)で児童労働の実態を暴く。もちろん、これだけではない。読者はそれを読んで驚き、呆れ、怒る。 一九〇六年,セオドア・ルーズベルト大統領が政財界の腐敗を暴き立てる彼らを「マックレーカーズ(Muckrakers)」と揶揄する。それはジョン・バニヤンの寓意物語『天路歴程』に登場する人物で,肥やしばかりを仰き続けて天上の神の恩寵に気づかぬ「肥やし熊手を持った男(The man with a muckrake)」に由来し、下ばかり見て、あら捜しをする連中という意味である。湛山もこれを原書で読み、『私の読書医術』(一九五二)において記憶に残っていると述懐している。ルーズベルトは社会改革に後ろ向きだったわけではない。むしろ、公共の利益のために政府は積極的に関与する「スクエア・ディール」とうスローガンの下、改良主義を唱え、有権者からの期待も高い政治家である。実際、当初はこの第二六代大統領もマックレーカーズに好意的だったが、次第に彼らに生地の改善を望むようになる。一九〇六年、『コスモポリタン』二月号にデヴィッド・グラハムによる「上院の裏切り(The Treason of the Senate)」なる記事を目にした大統領は、三月一七日、ナショナル・グリッドアイアン・クラブの夕食会でこの手のジャーナリズムを激しく批判している。これが報道関係者の間で話題となったため、彼は、同年四月一四日、連邦の下院のビル定礎式の記念講演として醜聞暴きを「マックレーカーズ」と糾弾し、翌日、『ニューヨーク・トリビューン』他各紙がそれを大々的にとり上げ、その名称が世間に広まっている。 しかし、一九〇六年、そのルーズベルトもショックを受けるマックレーカーズ作品が発表される。それがアップトン・シンクレアの『ジャングル』である。この小説は社会に衝撃を与え、アメリカの歴史を変える。 舞台はシカゴの食肉工場で、労働者の多くは後発移民のリトアニア人である。その労働環境たるや、反吐をもよおすほど不潔だ。労働者が肉を煮る大鍋に落ちたのに、そのまま処理され、人肉が市場に出回ってしまった、腐っているとクレームがついて回収されたハムやソーセージに薬品を注入して再出荷した、倉庫内の製品の上にネズミの糞が大量に溜まっていたなどの記述に溢れている。 これは、ルポではないが、丹念な調査に基づいており、決して誇張やでまかせが書かれているわけではない。この自然主義文学の代表作を通じて、シンクレアは、このような労働環境で働かざるを得ない移民に同情を寄せ、労働者の待遇改善を訴えている。 『ジャングル』を読んだアメリカの人々は食品製造の不衛生さに激怒し、食肉産業と当局へ抗議や非難が殺到する。一九〇六年、怒り狂った大統領と世論に押された議会は、慌てて、食肉検査法と純粋薬品製造法を成立させる。前者は精肉業者への衛生規制ならびに精肉工場への連邦政府による検査の義務付けの法律であり、後者は粗悪および健康被害のある食品と薬品の製造・輸送・販売の禁止を定めている。これは『ジャングル』発表からわずか半年後の出来事である。 マックレーカーズほど劇的ではないが、T・H・A・ドライサーやスティーヴン・クレインなどの高い文学性を持った自然主義文学者たちも社会改良を目指して作品を著わしている。ドライサーの『アメリカの悲劇』は、チェスター・ジレットがニューヨーク州北部のビッグ・ムース湖で同僚の女工グレース・ブラウンを殺害した一九〇六年の事件が直接的なモデルになっている。ドライサーは、長年に亘って殺人事件を調べていく中で、これと共通の特徴があるケースが多いことを発見する。カネと色の欲望にとりつかれた貧乏な青年が金持ちの令嬢と結婚をするために、邪魔になった自分と似たような境遇の貧しい恋人を殺害する。ドライサーは、こうした事件をアメリカ社会の歪みがもたらす「悲劇」として描き出す。あくまでも真の主役は今のアメリカ社会である。 こうしたタイプの殺人事件が実際に複数起きていたとしたら、確かに当時のアメリカ社会特有の「悲劇」と呼べるだろう。河合幹雄は、『日本の殺人』において、一九五九年版司法研修所調査叢書第五号『殺人の罪に関する量刑資料上・下』を読み解くと、少なくとも高度経済成長に向かう一九五〇年代日本にはないと指摘している。この資料は、司法試験に合格した研修生向けに、何百件にも及ぶ事例について被告の生い立ちも含めた事件の背景ならびに量刑の理由などが詳細に解説している。別れたい側が邪魔になったス手を殺すケースはただの一つもなく、別れたくない側がつねに加害者である。 この『アメリカの悲劇』は一九三一年(昭和六年)に映画化され、それを見た小林秀雄が原作よりいいと主張したのに対し、谷崎潤一郎が『文章読本』の中で、原文を引用して、ドライサーを擁護している。谷崎は、文学史上では、反自然主義に区分されているが、この一件からも日本の自然主義が近代文学の「神髄」を理解していなかったことがわかる。 アメリカの自然主義文学こそが湛山にとってあるべき姿である。 湛山も、『観照と実行』(一九〇九)において、生活していくには、「伝承」と「新要求がある以上に、「真理」や「理想」は時と場所によって変化すると言っている。日本の自然主義文学は社会改良には無関心だったが、「観照と実行」の関係を論じている。「観照と実行」、すなわち「理論と実践」が一致しなければならない、もしくは分離していてかまわないという議論は、「真理」や「理想」をも固定化して考えているにすぎない。後に登場する「正治と文学」や「芸術と実生活」というテーマも同じ構造を持っている。アメリカの自然主義文学のほとんどがジャーナリストである。それは、日本と違い、学者や学生が著わすものではなく、社会性のあるジャーナリストの小説である。社会が近代化したことで新しい人間が生まれ、そこに多くの矛盾や葛藤が生まれ、それを解決するためには、さらなる社会変革が必要だ。 湛山はジャーナリストに転身せざるをえなかったが、『「故郷」の訂正と我が官憲の性質」(一九一二)で次のように述べる文芸批評家のすべきことは以後の彼の活動にも反映されている。 我が邦は、今やどこの方面から考えて見ても、何うしても、政治的乃至社会的革新の時期に近づいておる。而してこの時に当って、我れ等国民に必要な物は、この革新を最も合理的に合法的に行うべき近代の批評的精神であるが、この精神を国民に鼓舞するものは、実に文芸思想家の直接の任である。 〈了〉 参考文献 石橋湛山。『石橋湛山評論集』、岩波文庫、一九八四年 石橋湛山、『湛山回想』、岩波文庫、一九八五年 谷沢永一編、『石橋湛山著作集4』、東洋経済新報社、一九九五年 伊藤整、『日本文壇史1』、講談社文芸文庫、 柄谷行人編、『近代日本の批評〈3〉明治・大正篇』、講談社文芸文庫、一九九八年 河合幹雄、『日本の殺人』、ちくま新書、二〇〇九年 姜克實、『石橋湛山』、丸善ライブラリー、一九九四年 増田弘、『石橋湛山』、中公新書、一九九五年 DVD『エンカルタ総合大百科2008』、マイクロソフト社、二〇〇八年 佐藤清文、『経済と文学』、二〇〇九年 http://hpcunknown.hp.infoseek.co.jp/unpublished/el.html |