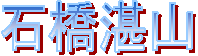Copy Right and Credit 佐藤清文著 石橋湛山
初出:独立系メディア E-wave Tokyo、2007年10月16日 本連載の著作者人格権及び著作権(財産権)は すべて執筆者である佐藤清文氏にあります。 リンク以外の無断転載、無断転用などをすべて禁止します。 |
|
|
第三節 湛山の歴史記述 まず、湛山は近代のヨーロッパの歴史を要約するが、その際、彼は新しい技術の開発・改良を次のように重視している。 近代の世界において、個人主義、自由主義、あるいは資本主義等といわれて居る一連の思想およびこれに基づく機構は、どうして興って来たかと考えますに、これは大ざっぱに申して、近代の産業技術の進歩と、これに伴う物資の豊富な生産を動力として発生したものだといえると存じます。 歴史記述には多様なアプローチがありうる。産業革命を中心とした近代の考察においても、都市と農村の関係、農業革命による人口増加、交通革命などあらゆる視点が可能であり、技術もその一つにすぎない。他の戦時中のテキスト同様、『百年戦争の予想』は検閲を意識したと見られるレトリックがいくつか見られるため、それを考慮して然るべきである。その点を別にしても、湛山が技術に焦点を合わせているのは、戦略的だと考える必要がある。 湛山は、『百年戦争の予想』の後半部分で、歴史記述を続けた後、厳しい官僚批判を展開している。それは官僚制一般と言うよりも、当時、戦時体制を主導した「革新官僚」のことであろう。彼らは東亜新秩序や新体制運動を支える観念論的な歴史観と結びつき、行政を仕切っている。彼らを批判するには、個々の政策を叩くだけでは不十分である。と言うのも、それらは、その妥当性はともかく、巨大な体系的歴史哲学に立脚しており、有機的につながっているからである。湛山は、国家を牛耳ろうとしているこの新しい官僚たちを根本的に批判するために、その根拠を切り崩そうとしている。 日本の近代官僚機構が真に機能するのは、実は、大正に入ってからである。第一次世界大戦後の1920年代、日本では急速に都市化・大衆化が進み、水やエネルギーの利用など新たな政治課題が生まれ、政治がそれに応えることが急務となる。政党政治がこの時期に始まるのは決して偶然ではない。政治行政への需要の増加が政党の重要性を高めることになっている。 政党政治が機能不全に陥った1930年代、政党に代わって、政策の総合的・計画的立案を行う新たな統合主体、すなわち「国策統合機関」の設置への動きが活発化する。「統合」とは行政国家化を意味し、究極的には官僚による「統制」につながる。1935年、内閣総理大臣直轄として置かれた内閣調査局がその中心となっている。 紆余曲折を経て、日中戦争の勃発を背景に、1937年10月、海軍・大蔵・商工各省による実務機関創設の運動が功を奏し、内閣調査局を前身とする企画庁が企画院へと再編される。これは、政策全体の統合主体を構想した陸軍案が斥けられたということでもある。 企画院は官界では、大蔵省や内務省と違い、本流ではなく、傍流にすぎない。そこで自らの政策の正当性をアピールするための理論を必要とする。近代制度の確立の過程で、内務省は国土開発政策を一手に握ってきたが、時代の変化や社会の要請と共に、専門化した新しい省庁が誕生し、その権限が縮小する。 近衛は日中戦争の意味づけのために、1935年11月3日、次のような「東亜新秩序」の声明を公表している。 この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。 帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更正の実を挙げ、新秩序の建設に来り参するに於ては敢て之を拒否するものにあらず。 帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟邦諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。 惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。 茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す 企画院はその正当化と地政学を結びつけて国土政策を編み出し、近衛内閣で優勢となる。内務省が都市から地方、さらに日本全体へという中心から周辺への方向性を持っていたのに対し。企画院は満州や中国から本土へという周辺から中心を向かう認識を示している。東亜新秩序から発展した大東亜共栄圏のイデオロギーではその傾向が顕著となり、企画院はさらに重要視される。 革新官僚たちの依拠する理論はヘーゲル主義的に解釈されたマルクス主義である。その正反合の弁証法的止揚に基づく壮大な体系性を持った哲学の枠組みを利用することにより、総合的・計画的な政策を実現する統合主体としてヘゲモニーを獲得したと言って過言ではない。革新官僚がモデルにしたのはソ連型の計画経済であり、実際、密かに、彼らはマルクス主義研究を行っている。 「統合」自体すでにヘーゲル主義的発想である。G・W・F・ヘーゲルの『精神現象学』によれば、一切のものを包括する絶対者はその意味で普遍的であるけれども、個別的なものを離れているならば、抽象的な理屈にすぎないのであって、普遍と個別が特殊な契機に媒介されて統一された具体的普遍が、真に現実的なものである。ヘーゲルは、対立や矛盾を決して斥けない。 湛山はこの観念論に挑戦する。彼は田中王堂のプラグマティズムに影響されたことを認めている。田中王堂は、プラグマティストの中でも、ジョン・デューイの思想を継承したことで知られている。湛山の歴史記述にはデューイの方法論が繁栄しているが、これは非常に重要である。 「プラグマティズム(Pragmatism)」という名称は、アメリカの思想家チャールズ・サンダース・パースがイマヌエル・カントの『純粋理性批判』に登場する概念から考案している。カントは無条件的な動機主義を「プラクティッシュ()Ptaktisch」、条件付きの動機主義を「プラグマティッシュ(Pragmatisch)」と呼び、前者を重視している。しかし、パースは後者を選び、自らの思想を「プラグマティズム」と命名する。パースの記号論は「転倒されたカント主義」と言えるだろう。 デューイはこのアメリカの哲学に接する前の1880年代、流行していたヘーゲル主義の立場をとり、ヘーゲル主義を標榜する学術誌に論文を投稿したりしている。アメリカで受容されたのは、特に、定立=反定立=総合という弁証法的方法論が確立された『論理学』であり、南北戦争などによる連邦の分裂の危機を統合したいという願望から読まれていたと推測されている。 湛山の歴史記述はこのデューイによるヘーゲル主義批判を踏まえている。湛山は、この方法論をド具に、19世紀の百年戦争、20世紀の百年戦争を分析し、日本の戦時体制を主導するイデオロギーを批判していく。
|